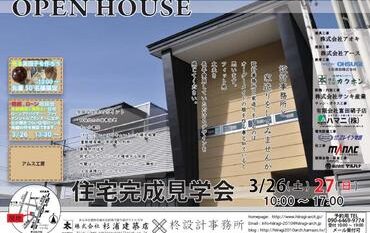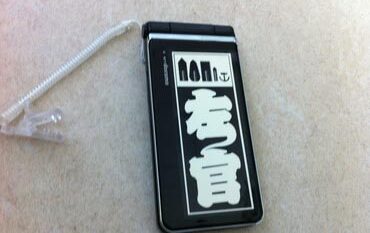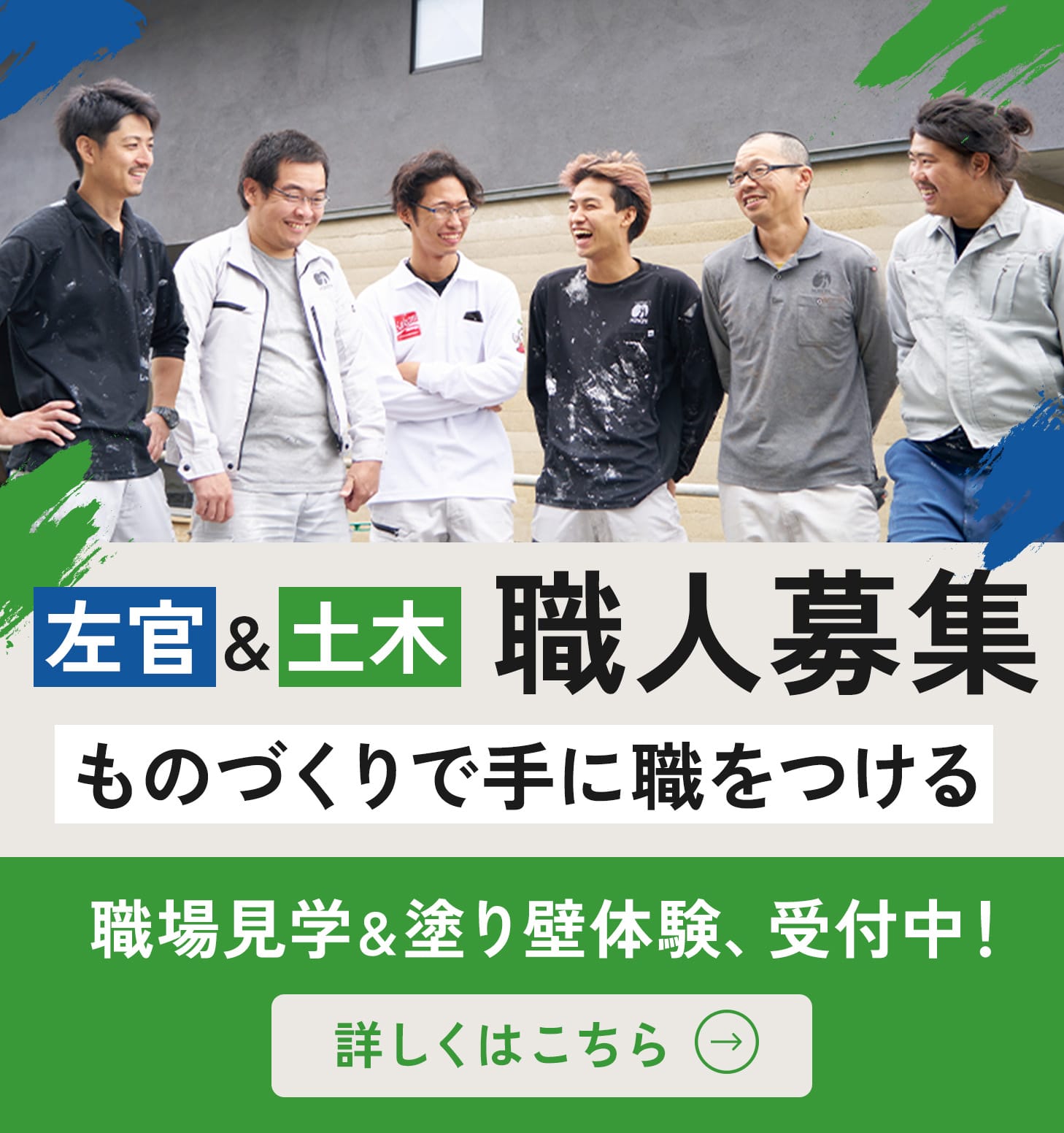「左官を考える会in常滑」シリーズは今回で最後です。
2日間にわたる講習会の中で、初日の夕方に記念講演会を行いました。
講師は土どろんこ館館長、大学教授、写真家、左官職人、執筆家の計5人でした。

テーマは「三和土(たたき)」について、違う職業の方がひとつのテーマについて語っていただきました。
特に興味深かった内容に、「長七たたき」ということについて。
長七とは「服部長七<1840~1919,三重県出身>」のことで、非常に硬い三和土を発明し、三和土で護岸工事などを行った方のようです。ちなみに「三和土」とは、一般的に「土」「石灰」「にがり」の3種類を配合し、少量の水で練ったものを叩いて固める仕上げです。
三和土はセメントよりも固まる時間も遅く、初期強度も弱いのですが、塩分には強く、徐々に強度があがり、石のように固まっていきます。さらに、セメントのように中性化することがないので、長い年月強く固まっています。その性質を利用し「長七」が護岸工事を行ったそうです。今でも、彼が行ったこの「長七たたき」は現在でも「四日市港の潮吹き防波堤」で見ることができるとか
さらにさらに、現在この「長七たたき」が見直され、INAXの基礎研究所がカンボジアのアンコール遺跡のひとつ「アンコールトム」で基礎の修復工事を行っているそうです

セメントを使用しない理由は、長期間の耐用年数がないからだそうです。
ところで、ある講師がこんなニュアンスのことをおっしゃっていました。
「現代は強固なものを作る技術は進歩した。しかし、柔らかいものを作る思想も大切ではないか。そして、土のような柔らかいもののほうが美しいのではないか。」
・・・たしかにセメントのように簡単に固まってくれるもののほうが、現代社会の方が合っているのかも知れません。だけど、柔らかいものには心のやすらぎのようなものだったり、あたたかい人のぬくもりのような感じのものだったり、心や精神的なようなものがあるのかもしれません
そして、最後に三和土を科学するような話もありました。
・どのようなしくみで三和土が固まっていくのか?ポゾラン反応について。
・材料の配合をどのように考えていったらよいのか?
・石灰は「消石灰」「石灰クリーム」「生石灰」のどれがよいのか?
・にがりの代用品「塩化カルシウム」「塩化マグネシウム」のどちらがよいのか?
・そもそもにがりを入れる意味とは?
などなど。。。
三和土について非常に考えさせられた記念講演会でした